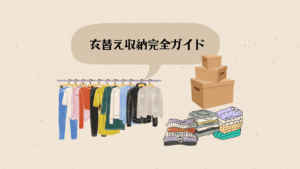どうも~、ももんぬです~。今回は夏服のしまい方についてお話しますね~。
9月も後半になると、着るものに迷う日が増えてきませんか? Tシャツやブラウスを片付けて、カーディガンや薄手のニットを出す準備をする人も多い時期だと思います。
とはいえ、この片付け方をちょっと間違えると、翌年取り出したときに「うわ、黄ばみやカビが…」ってガッカリすることになるかもしれません。
実は、こうしたトラブルの多くは、しまい方のちょっとした工夫で防げるんです。お気に入りの服を長く大切に着るために、片付ける前の準備や収納のときに気をつけたいことを知っておきたいですよね。
この記事では、お気に入りの夏服を来年も気持ちよく着られるように、しまい方のポイントをわかりやすくご紹介します。
- 結論:しまう前に皮脂落とし → 完全乾燥。防虫剤=上/除湿剤=下でOK
- 前処理:襟・袖の皮脂は酸素系漂白(40℃)つけ置き→すすぎ(※洗濯表示を確認)
- 乾燥:陰干しで湿気ゼロ最優先(風を通し一晩置きまで)
- 収納:Tシャツは立て収納/プラケースは除湿剤“下”+防虫剤“上”
- NG:柔軟剤の残り香・漂白臭の残留・長期圧縮(シワ/復元不良)
※本記事にはアフィリエイト広告(PR)が含まれています。商品選びの参考にご活用ください。
夏服をしまう前に必ずやるべき準備
夏服を片付けるときに一番大事なのは、“しまう前のひと手間”。これをサボってしまうと、翌年取り出したときに「うわ、黄ばみやカビが…」なんて残念なことになりがちです。
夏に着た服は、一見きれいに見えても汗や皮脂の汚れが残っていることが多いんですよね。しかも洗ったあとでも、少しでも湿気が残っていると、収納ケースの中でカビやニオイの原因になってしまいます。
だからこそ「もう着ないからしまう」じゃなくて、「来年も気持ちよく着るために整えてからしまう」という意識が大切。ここからは、そのために必要な準備についてお話ししていきます。
黄ばみ・汗ジミを落とす洗濯のコツ
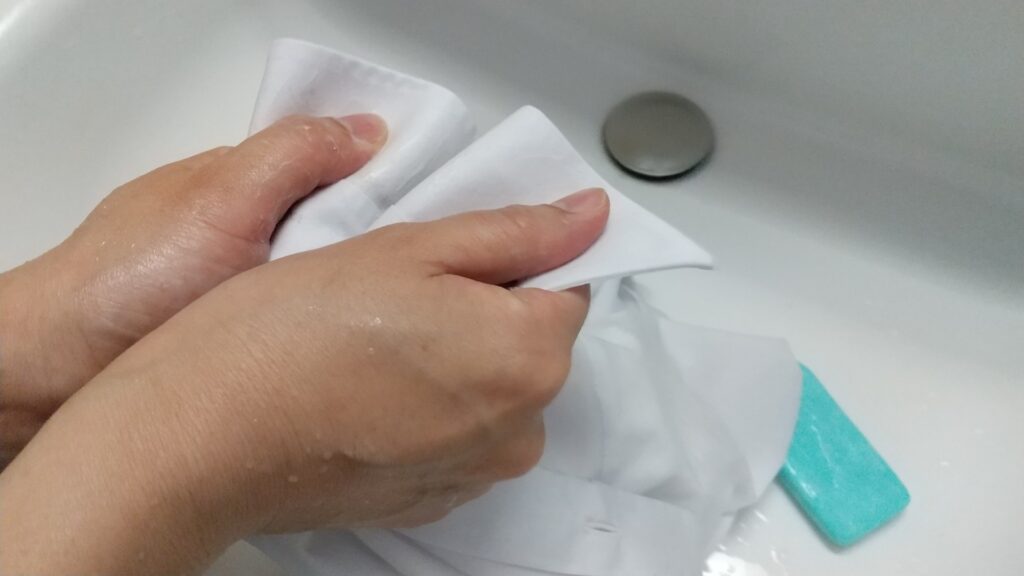
夏服は見た目がきれいでも、実は汗や皮脂の汚れがしっかり残っています。これを落とさずに片付けてしまうと、時間が経つにつれて黄ばみやニオイとなって浮き出てくるんです。特にTシャツやブラウスの襟、袖口、脇の部分は要注意。
おすすめは 酸素系漂白剤を使ったつけ置き。40℃前後のお湯に溶かして30分ほど浸けると、汗ジミや皮脂汚れがスッキリ落ちます。部分的に汚れが目立つところは、固形石けんを直接こすりつけてから洗濯すると効果的です。
さらに、洗濯後に軽くアイロンをかけておくと、布地に残った湿気を飛ばせるうえにシワも防げて一石二鳥。ちょっとしたひと手間ですが、翌年の仕上がりがぐっと変わります。

汗ジミや黄ばみって、出てきてから落とそうとすると本当に手強いですよね。「ちゃんと洗ったはずなのに…」と感じるときは、しまう前のひと工夫が足りていないサインかもしれません。
襟・袖・脇だけでも、酸素系漂白剤のつけ置きや固形石けんでの部分洗いをしておくと、翌年の黄ばみ・ニオイをかなり防げます。洗濯後はしっかり乾かしてから収納へ。
ももんぬもこの習慣にしてから、白Tの“がっかり黄ばみ”がほとんどなくなりました。未来の自分を助けるつもりで、「しまう前のケア」だけは丁寧にしてあげてくださいね。
完全に乾燥させるのが鉄則


もうひとつ大事なのが「乾燥」。衣類にわずかでも水分が残っていると、収納中にカビや嫌なニオイを発生させる原因になり、黄ばみよりも深刻なトラブルになることもあるんです。
理想は天日干しでしっかり乾かすこと。秋は空気が乾燥してくるので、風通しの良い場所でしっかり干せば安心です。乾燥機を持っているなら仕上げに軽くかけてもOK。
さらに安心したい人は、クローゼットにしまう前にもう一晩陰干しして、しっかり乾いたことを確認してから収納しましょう。少しの工夫ですが、これで翌年のカビやニオイのリスクはぐっと減らせます。
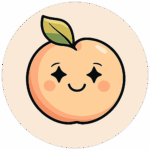
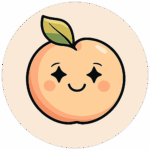
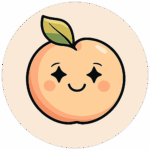
洗濯した服って、触った感じが乾いていても“芯のほう”に湿気が残っていることが多いんですよね。特に厚手のTシャツやデニムは、表面が乾いていても中がしっとりしていることも。収納後にカビ臭くなるのは、たいていこの残り湿気が原因なんです。
秋の空気は乾いているので、風通しのいい場所で一晩しっかり陰干ししてからしまうのがおすすめ。仕上げに軽くアイロンをかけると、熱で菌やニオイも防げて一石二鳥です。
ももんぬも以前「もう乾いたかな?」で油断して失敗したことがあって、それ以来“乾かしすぎるくらいでちょうどいい”を合言葉にしています。ほんの一晩のひと手間で、翌年の快適さがまるで違いますよ。
やってはいけないNG収納
夏服をきれいにしまうには、正しい方法を知ることも大事ですが、実は「やってはいけない収納」を避けることのほうが効果的だったりします。
衣替えって面倒な作業だけに、ちょっとした油断や「まぁいいか」でやってしまう行動が多いんですよね。洗ったかどうか確認せずにしまったり、ビニールに入れっぱなしにしたり…このくらいいいかな、という油断が結果的に服を傷める原因になってしまいます。
ここでは、そんな“やりがちだけど避けたい収納法”を整理しました。普段の自分の片付け方と比べながらチェックしてみてください。
洗わずにそのまましまう


夏服は一度しか着ていなくても、汗や皮脂汚れがしっかり残っています。特に脇や襟、背中など、汗をかきやすい部分は見えない汚れが多いもの。この汚れをそのまま収納すると、時間が経つにつれて酸化し、翌年取り出したときに黄ばみや嫌なニオイとして浮き出てきます。
見た目にきれいでも「着たら必ず洗う」が基本です。洗濯できない素材はクリーニングに出すなど、ひと手間を惜しまないことが長く着るためのコツになります。



衣替えのときって、「このくらいなら洗わなくても平気かな?」が一番こわい落とし穴なんですよね。汗や皮脂は見えなくても残っていて、しまっているあいだに酸化して黄ばみやニオイに育ってしまいます。
ももんぬは、「とにかく一回でも着たら洗ってから収納」を徹底するようにしています。クリーニングに出したものも、戻ってきたらすぐしまわず、状態をチェックしてから。
少し手間は増えますが、その分、翌年のガッカリがなくなって、気持ちよく新たなシーズンのスタートを切れるんです。
ビニール袋に入れっぱなし


クリーニングから返ってきた服にはビニールカバーがかかっていますよね。ホコリ防止になりそうですが、実はそのまま収納するのはNGです。ビニールは通気性が悪いため湿気がこもりやすく、結果的に黄ばみやカビの原因になってしまいます。特に薄手でデリケートな夏服は、湿気を含んだままになると生地が傷むリスクも高まります。
収納する前に必ず外して、不織布カバーなど通気性のあるものに掛け替えるのがおすすめです。これならホコリを防ぎつつ湿気も逃がせるので、安心して保管できます。



クリーニングのビニールって、「このまましまえば清潔そう」と思いがちなんですが、実は湿気を閉じ込める“カビ予備軍カバー”なんですよね。特に夏服は生地が薄くてデリケートだから、もったいないトラブルになりがちです。
収納するときはビニールを外して、不織布カバーや通気性のあるカバーに掛け替えるのがおすすめ。ホコリは防げて湿気は逃せるので、黄ばみやカビ対策としても優秀なんです。
除湿剤や防虫剤を使わない


収納ケースやクローゼットにそのまま服を詰め込むのも実は危険。湿気が多いとカビが発生しやすく、また虫が入り込むと大事な服に穴が空いてしまうこともあります。特に天然素材の綿や麻は湿気を吸いやすく、ウールは虫食いに狙われやすいので注意が必要です。
収納ケースやクローゼットには、必ず除湿剤や防虫剤を入れておきましょう。数か月ごとに交換すれば、保管中のリスクを大きく減らせます。



クローゼットって、「とりあえずしまって閉めておけば安心」と思いがちですが、実は湿気や虫にとってはすごく居心地のいい場所なんですよね。何もケアしていないケースや押し入れは、いつの間にかカビ・虫食いリスクが高くなりやすいです。
ももんぬは、防虫剤と除湿剤を“セットで同じタイミングに交換する”ように決めています。ケースの底に除湿剤、衣類の上やクローゼット上部に防虫剤を置いておけばOK。
置き方と交換サイクルをパターン化しておくと、難しいことを考えなくても、自然と服を守れる状態がキープできますよ。
ギュウギュウに詰め込む


スペースが足りないからといって、衣装ケースやクローゼットにギュウギュウに詰め込むのもNG。服同士が押しつぶされてシワや型崩れの原因になるだけでなく、通気性が悪くなり湿気がこもってしまいます。
どうしてもスペースが足りない場合は、圧縮袋でかさを減らしたり、シーズンごとに着ない服を見直して整理するのもおすすめ。収納の工夫ひとつで、服の持ちは大きく変わります。



クローゼットやケースがパンパンだと、「収納できた」感じはするのに、中の服は実はずっとストレス状態なんですよね。
通気性が悪くなって湿気がこもり、シワ・型崩れ・カビやニオイの温床になりがち。指一本も入らないラックや、押し込んだ引き出しは、黄ばみケアより先に見直したいポイントです。
ももんぬは「ギュウギュウになったら圧縮袋を使うor着ていない服を手放す」のどちらかをセットで考えるようにしています。掛ける服はハンガー同士のあいだに指一本分の余裕を。
たたむ収納も八分目くらいを意識するだけで、服の持ちも見た目のスッキリ感も、変わってきますよ。
▼衣類の虫食いやカビ対策が気になる方はこちらへ。


正しい夏服のしまい方ステップ
ここまで、しまう前の準備やNG収納について見てきました。「気をつけなきゃ」と思うポイントは分かったけれど、じゃあ実際にどう片付けていけばいいのか――ここが一番知りたいところですよね。
正しい手順を踏めば、来年の衣替えのときに「きれいなまま!」と気持ちよく服を取り出せます。逆に、順序をあいまいにしたり自己流で片付けてしまうと、せっかくのお気に入りが残念な状態になってしまうことも。
ここでは、服の種類ごと・収納場所ごと・防虫や除湿の工夫まで、夏服をきれいに保つためのステップを整理しました。ひとつずつ確認しながら進めていけば、誰でも簡単に「失敗しない収納」ができるようになりますよ。
服の種類ごとのたたみ方と収納方法
夏服といっても、Tシャツやシャツ、ブラウス、ワンピースなど種類によって適したしまい方は違います。同じ「たたんでしまう」でも、服の形や素材によって気をつけるべきポイントがあるんです。ここでは代表的な服ごとに整理してみました。
- Tシャツ
→厚みをそろえてたたみ、立てて収納すると型崩れを防ぎながら一目で見やすくなります。白Tは特に黄ばみやすいので、完全に乾かしたあとでケースに入れるのが安心。 - シャツ/ブラウス
→シワになりやすいので、基本はハンガーに掛けるのがベスト。肩の形が崩れないように厚みのあるハンガーを選び、不織布カバーをかければホコリや光焼けからも守れます。 - カーディガンや薄手ニット
→ハンガーだと重みで肩が伸びやすいので、平たくたたんでケースにしまうのがおすすめ。通気性を確保するために、除湿シートを下に敷いておくとさらに安心です。 - パンツやスカート
→二つ折りにして立てて収納すれば型崩れが少なく取り出しやすいです。ハンガーに掛ける場合は、クリップ付きの専用ハンガーを使うとシワが防げます。 - ワンピース
→軽い素材はハンガーに掛けて保管。重みのある生地はたたんでケースに入れ、間に薄紙を挟むとシワ防止になります。このひと手間で翌年の状態が大きく変わるので、特にお気に入りは念入りに。



しまい方って“形や素材に合わせる”だけで、見た目も持ちも全然違うんですよね。
Tシャツは立てて並べると一目で選べて型崩れしにくいし、ブラウスやシャツは厚みのあるハンガーで肩を守るのがコツ。ニットやカーディガンは吊るさず平たくたたむことで、伸びやヨレを防げます。
ももんぬは、お気に入りほど「空気が通る場所」に置くようにしていて、重ねすぎず、除湿シートで湿気ケアも忘れません。収納って、見た目を整える作業じゃなくて“来年までコンディションを維持するための準備”なんですよね。
種類別に使い分け│Tシャツ収納・型崩れ防止ハンガー
収納ケース・引き出し・クローゼット別の保管法
収納する場所によっても注意すべきポイントは変わってきます。ケースはまとめやすいけれど湿気がこもりやすい、タンスの引き出しは便利だけど油断するとゴチャつきやすい、クローゼットは通気性があるけれど掛け方次第で型崩れしやすい…と、それぞれに長所と弱点があるんです。
そこで、「収納ケース」「タンスなどの引き出し」「クローゼット」 の3つのパターンについて、気をつけたい点と工夫のコツをご紹介します。
- 収納ケースにしまう場合
→通気性のある不織布や軽いプラスチックタイプを選ぶのがおすすめです。底には除湿シートを敷いて湿気を防止。ぎゅうぎゅうに詰めると通気性が悪くなるので、余裕をもたせましょう。 - タンスなどの引き出しにしまう場合
→よく使う服は上段や手前に、次の夏まで触らないものは下段や奥にしまうと効率的。仕切りやラベルを使っておくと、場所を変えても家族の誰にでもわかりやすくて便利です。 - クローゼットにしまう場合
→ブラウスやワンピースなどはハンガーに掛けるのが基本。掛けるときは少し余裕を持たせ、風通しを意識しましょう。シーズンごとに掛ける場所を入れ替えると、衣替えがスムーズになります。



クローゼットやケースを同列に、「全部の服の置き場」と考えると詰まりやすいんですよね。
ももんぬは、場所ごとに役割を決めてから入れるようにしています。クローゼット=“次シーズンの主力選手”、引き出し=“普段づかい&下着類”、ケース=“オフシーズンの予備枠”というイメージです。
この3つをなんとなく区別するだけでも、「どこに何をしまったっけ?」が減って取り出しやすくなります。ラベルやエリア分けで“人が見ても分かる収納”にしておくと、家族が片付けに参加しやすくなるのも地味に大きなメリットです。
シーン別に選びたい収納アイテム
防虫剤・除湿シートの正しい使い方
せっかくきれいにしまっても、湿気や虫の被害にあえば台無し。防虫剤や除湿シートを正しく使うことが、安心して服を保管するための対策の仕上げになります。
- 防虫剤
→薬剤は空気より重いので、クローゼットの場合は上部に置くのが基本。ケースの場合は衣類の上に置くと全体に薬剤が行き渡ります。複数種類の防虫剤を混ぜて使うのは避けましょう。 - 除湿シート
→収納ケースや引き出しの底に敷いて湿気を吸収させます。梅雨や夏の湿気をそのまま持ち込まないために、シーズン替えのタイミングで新しいものに取り替えるのがベスト。交換サイン付きのタイプだと忘れ防止になります。 - 組み合わせ方
→「まず湿気を取ってから、虫を防ぐ」という流れを意識すると効果的。除湿シートで湿気対策をしたうえで、防虫剤を配置するのが理想です。



防虫剤と除湿シートって、「なんとなく入れてる」状態だと、実は十分に守れていないことが多いんですよね。湿気が多いままだと薬剤の効きも落ちるので、「下で湿気を受け止める → 上から防虫成分を行き渡らせる」という順番を意識して配置してあげるのがポイントです。
ももんぬは、ケースの底に除湿シート、その上にたたんだ服、一番上に防虫剤を置く形を基本セットにしています。クローゼットも同じく上部に吊り下げタイプを。いろいろ混ぜて使わず、シーズンごとにまとめて交換するだけで管理がラクになって、「ちゃんと守れてる安心感」も違ってきますよ。
設置場所によって使い分けたい防虫剤・除湿剤
衣替えの前にそろえておきたいアイテム
衣替えをスムーズに進めるには、正しい手順を知るだけでなく、その準備を支えてくれるアイテムをそろえておくことも大切です。通気性のいい収納ケース、黄ばみを防ぐための洗剤や漂白剤、そして湿気や虫をブロックする防虫・除湿グッズ――。これらを味方につけるだけで、収納の質がぐっと上がり、来年の衣替えも快適になります。
そこで、ここからは ももんぬがおすすめしたいグッズ をいくつかピックアップしてご紹介します。ここまで読んでいただいた記事内の商品写真からもそれぞれの詳細ページにアクセスできるので、そちらもぜひチェックしてみてくださいね~。
不織布ケース(通気性◎)
衣替えの収納でまず用意したいのが、不織布ケース。プラスチックケースに比べて通気性が良く、湿気を逃がしやすいのでカビやニオイ対策に効果的です。軽いので移動もラクで、季節ごとの入れ替えにも向いています。



服をしまうときって「汚れやシワ」に目が行きがちですが、実は湿気を逃がす“通気性”こそが服を守るカギなんです。不織布ケースは空気をほどよく通してくれるので、カビやニオイの発生をぐっと抑えられます。軽くて扱いやすく、棚上や押し入れにも収まりやすいのもポイント。
ももんぬは、不織布ケースの前面にラベルを貼って「中身が見える収納」にしておく派です。見た目もスッキリして探す手間も減るので、衣替えのときの“どこいった?”が激減します。少しの工夫で、次のシーズンの自分がびっくりするくらいラクになりますよ。
黄ばみ防止洗剤・漂白剤
服をしまう前の“しまい洗い”にあると安心なのが、黄ばみ防止タイプの洗剤や酸素系漂白剤。白Tやブラウスはどうしても皮脂汚れが残りやすく、来年取り出したときの黄ばみの原因になります。ここでひと手間かけておくだけで、服の寿命がぐっと延びます。



白Tやブラウスって、しまう前はきれいに見えても、実は皮脂汚れが残っていることが多いんですよね。これが時間とともに酸化して黄ばみになるので、収納前の“しまい洗い”こそ一番の予防策です。黄ばみ防止タイプの洗剤や酸素系漂白剤を使うだけで、翌年の白さがまるで違います。
ももんぬは、襟・袖の部分だけ専用洗剤で軽くもみ洗いしてから、全体を漂白剤で仕上げています。日頃から皮脂汚れをしっかり落とす習慣をつけておくと、来年取り出したときに「わ、まだ真っ白!」ってうれしくなるんですよ。
防虫・除湿アイテム
最後に欠かせないのが、防虫剤や除湿アイテム。どんなにきれいにたたんでも、収納環境が悪ければ台無しです。正しく配置すれば、収納中の安心感がぐっと高まります。



防虫・除湿グッズは「きれいにしまった服を守るガード役」だと思って使うと選びやすいですよ。カバータイプでほこりと虫をまとめて防げるものや、天然成分でにおいが柔らかいタイプなど、収納場所や家族の好みに合わせて組み合わせてOKです。
ももんぬは、防虫剤と除湿シートをセットで配置して、「ここはちゃんと守れている」という状態をつくるようにしています。同じメーカーやシリーズでそろえると、置き方も分かりやすくて管理もしやすいですよ。
まとめ|来年も気持ちよく着るために
夏服をきれいにしまうコツには、難しいテクニックは必要ありません。
- 汚れをしっかり落としてからしまう
- 完全に乾かして湿気を残さない
- 通気性のあるケースやカバーを選ぶ
- 防虫・除湿アイテムで環境を整える
この流れを守るだけで、来年取り出したときに「うわ、きれい!」と気持ちよく袖を通せるようになります。正直ちょっと面倒な作業ではありますが、服を守るひと手間をかけておくだけで、翌年の自分がラクできるんですよね。



衣替えって、「面倒だけどやらなきゃ」で終わらせると、どうしても“今年もなんとなく片付けた服たち”が増えてしまうんですよね。でも、汚れ落とし・乾燥・通気性・防虫&除湿、この4つを意識しておくだけで、次の夏に取り出した服が“ちゃんときれいなまま”で迎えてくれます。
ももんぬも、以前は黄ばみやカビで泣く泣く手放した服がいくつもあって、「しまうときの数分を惜しまなければ守れたのに…」と痛感しました。だからこそ、読んでくれているあなたには、“未来の自分が気持ちよく袖を通せる状態まで”を衣替えのゴールにしてほしいなと思っています。